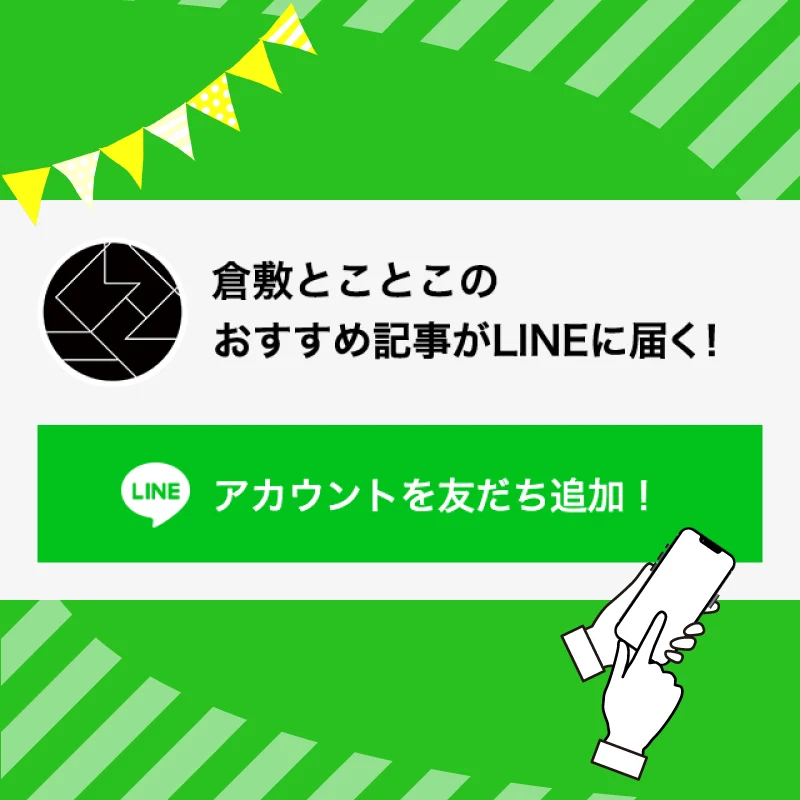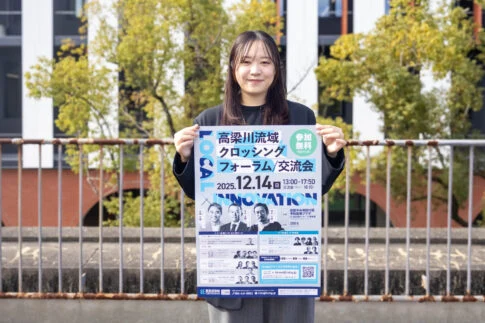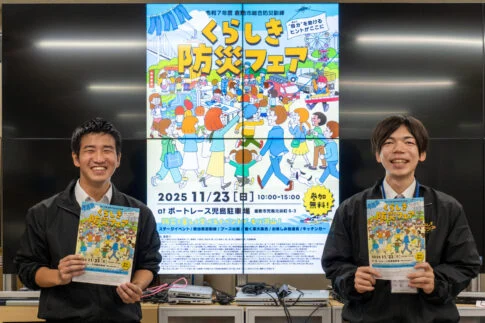岡山桃太郎空港、桃太郎大通り、桃太郎線(吉備線)、桃太郎ぶどう……。
「岡山といえば桃太郎」を簡単に連想できるほど、岡山県には桃太郎にまつわるものであふれています。
岡山県は桃の一大産地であり、桃太郎の必須アイテムである「きびだんご」は定番のお土産です。岡山県出身の筆者も、「岡山といえば桃太郎」と当たり前のように思い、これまで深く考えたことはありませんでした。
しかし、すべての物事には理由があるものです。
なぜ岡山県では、桃や桃太郎がこれほど日常に溶け込んでいるのでしょうか。
その謎を公益財団法人大原芸術財団 倉敷考古館 研究員の伴祐子(ばん ゆうこ)さんが教えてくれました。
記載されている内容は、2025年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
日本遺産における岡山の桃
桃から生まれた桃太郎が、犬・猿・キジを連れて鬼ヶ島に鬼退治に行く。
有名な「桃太郎伝説」のストーリーです。
岡山は桃太郎伝説発祥の地とされており、日本遺産には「桃太郎伝説」の生まれたまち おかやま (以下、「桃太郎伝説」と記載)のストーリーが登録されています。

桃太郎伝説の話の前に、日本遺産について簡単に紹介しましょう。
日本遺産とは、地域の歴史的魅力や特色を通じて、日本の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が「日本遺産」として認定したものです。地域に点在する遺産を「面」として活用し、発信することで、地域活性化を図ることを目的としています。
つまり、個々の文化財を結び付けて、ひとつのストーリーとして魅力を発信するのが日本遺産の特徴です。
倉敷市では三つのストーリーが日本遺産に登録されています。
桃太郎伝説

倉敷市も関わりのある「桃太郎伝説」は、29の構成文化財から成り立っています。
桃太郎のモデルとされるのが、「吉備津彦命(きびつひこのみこと)」です。
現在の岡山県と広島県東部にあたる吉備の国には、その昔、温羅(うら)と呼ばれる鬼がおり、山の上に城を築き村人を襲い悪事を重ねていました。国を治めるために大和政権から派遣された吉備津彦命は、温羅退治の命令を受けることに。
吉備津彦命の温羅(鬼)退治については、日本遺産ポータルサイトから引用します。
吉備津彦命は、吉備の地に降り立ち、吉備の中山に陣を構え、その西の小高い丘の頂には温羅の矢を防ぐ巨石の楯を築いた。弓の名手であった命は、岩に矢を置き温羅に向かって矢を放つ。温羅も応戦し城から矢を放つが、互いに放った矢は何度も喰い合って落ちていった。しかし、命が力を込めて放った矢は、ついに温羅の左目を射抜く。温羅の目からは血が吹き出し、川のように流れたという。たまらず雉に化けて逃げる温羅を、鷹になった命が追う。温羅は雉から鯉に化けて血の流れる川に逃げたが、命は鷹から鵜となり、鯉を喰い上げ、見事に温羅を退治し、その首を白山神社の首塚にさらした。
この話に登場するものが、倉敷市でも日本遺産構成文化財として認定されています。
- 楯築遺跡
「西の小高い丘の頂には温羅の矢を防ぐ巨石の楯を築いた」跡 - 鯉喰神社
「鯉を喰い上げ」た場所


伝説と実際に存在するものが結びついている点が、桃太郎伝説の興味深いところです。
では、なぜ「桃」太郎と呼ばれているのでしょうか。