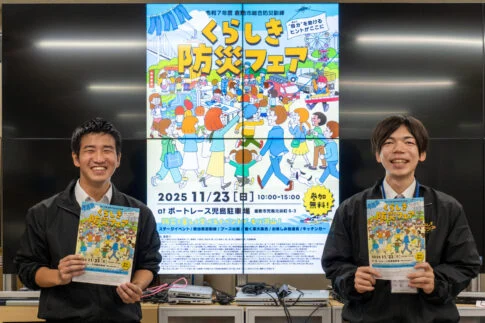下津井に生まれ、岡山県を代表する民謡といわれる「下津井節」。
江戸時代から下津井で歌い継がれてきた下津井節は、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」の構成文化財にも認定されています。
毎年9月には全国大会も開催されている下津井節ですが、出場者は年々減少し、若い世代の参加も減少気味です。
全国的に民謡が存続の危機に瀕(ひん)している今、下津井では下津井節を次世代へ受け継ぐための活動が始まっています。
下津井節を継承するかたがたの想いと、今後の展望を紹介します。
記載されている内容は、2025年10月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
下津井節とは

下津井節は、江戸時代から歌い継がれている民謡です。
かつて、北前船の寄港地だった下津井は、日本全国から商人が集まるにぎやかな街でした。北前船の乗組員と下津井の人々の間には多くの交流が生まれ、そのなかで伝えられた流行歌を、下津井らしくアレンジして生まれたのが下津井節です。
下津井節は、乗組員をもてなす際に歌われるようになり、さまざまな流行を取り入れながら徐々に下津井に定着していきました。
当時の下津井節は決まった歌詞がなく、歌う人の個性が現れる自由な民謡だったといいます。

下津井節は、下津井の人々の暮らしの一部として、自然に地域で受け継がれてきました。学校の運動会では、子どもたちが踊りと一緒に下津井節を披露することもあったそうです。
しかし、時代が進み、音楽が多様化するにつれて、民謡そのものに触れる機会が減りつつあります。現在、民謡を含む伝統芸能の後継者不足が日本各地で課題となっており、下津井節も例外ではありません。

下津井節の継承活動
下津井では、下津井節を守り、次世代に継承する活動が近年活発になってきています。
継承活動における「下津井節」とは、民謡としての唄・伴奏だけでなく、踊り(民舞)も含めた地域文化を指します。
2024年には、初の試みとして「下津井宵灯り」が開催されました。昔の風情が残る下津井町並み保存地区で、下津井節の歌と踊りを披露するお祭りです。

下津井宵灯りが始まる前、下津井節の振り付けを知っているかたは、わずか5名だったそうです。歌だけでなく、踊りも途絶えてしまう寸前の状況で、地域の人たちが団結し、継承に取り組みました。
当日は予想を上回る多くの観客が下津井を訪れ、盛況のうちに幕を閉じました。
下津井宵灯りは、今後も年に一度のお祭りとして開催されます。
さらに、下津井宵灯りの定例化にともない、下津井節の活動の場が徐々に増えてきています。
- 「下津井節あかでみぃ」の開催
- 着付けの講習会の開催
- 児島を中心に、市内イベントでのお披露目
- 下津井の小学校の授業に参加
数々の活動のなかでも特に注目したいのが、下津井節を気軽に体験できる「下津井節あかでみぃ」です。

下津井節の歌だけでなく、踊りや三味線の演奏も体験できます。初めてのかたでも参加しやすく、「下津井節あかでみぃ」をきっかけに下津井宵灯りに参加したかたが20名ほどいるそうです。
今後も開催されるので、気になるかたは、下津井宵灯りのInstagramを確認してください。

下津井節の継承活動をおこなう中心人物は、民謡歌手の津本ゆかりさん。
一連の活動の発起人です。津本さんに、下津井節への想いと今後の継承活動の展望について話を聞きました。