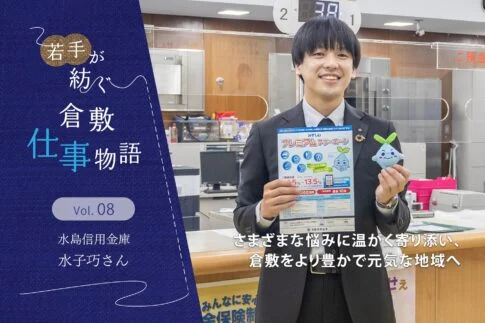倉敷市児島地域の南部にある海沿いの地区、下津井(しもつい)。
現在、漁業の町として知られ、タコなどの海産物が名産です。下津井の漁業の歴史は、非常に古いといわれています。
また近世になると北前船(きたまえぶね)が停泊するようになり、綿とニシン粕などの取引が活発におこなわれ、町には回船問屋(かいせんどんや)などが建ち並びました。
さらに備前と讃岐を結ぶ海路の拠点となり、瑜伽(ゆが)大権現・金毘羅大権現の「両参り」などで大勢の旅人が下津井を訪れたといいます。
現在でも下津井には、かつての港町としてのにぎわいを感じさせる、歴史ある建造物が多く残されています。そして下津井では、歴史ある町並みを守るために、人や地域の活性化に取り組んでいるのです。
下津井の港町としての歴史、町並みを守るための取組などについて掘り下げていきましょう。
記載されている内容は、2025年8月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
目次
下津井の町並みの概要

下津井は倉敷市児島地域南部に位置します。瀬戸内海と山地に挟まれた地形が特徴の地区です。
地区東部には瀬戸大橋が通っており、本州側の起点になっています。
下津井は古い時代から、下津井港(下津井湊)の港町として栄えました。地区内を東西に走る通り周辺には、古い建造物が多く残され、港町としての風情を今に残しています。
下津井の町並みの歴史
港町として古い歴史のある下津井。その歴史を紐解いていきます。
地理的環境から漁港として繁栄

もともと下津井港は、漁港として古くから栄えました。
現在の岡山県西部から広島県東部の沖合は、瀬戸内海のほぼ中央にあたります。東西からの潮の流れがぶつかり合う場所であることから、魚が豊富に捕れました。
さらに岡山県三大河川(高梁川・旭川・吉井川)などによって、内陸から豊かな栄養分が海に流れ込み、魚を育てます。
またかつて下津井の漁港として使われてきたのは、現在の祇園(ぎおん。祇の正式表記の偏は「礻」)神社がある岬の西側。岬から西に湾曲した入江状の地形で、地理的に港として絶好の場所でした。
下津井は漁業に適した地で、天然の良港だったのです。
江戸時代に北前船が寄港し商取引が活発に

下津井が新たな局面に移るのは、江戸時代。
下津井港に北前船が、停泊するようになったのです。
漁港として使われてきたのは、現在の祇園神社がある岬の西側でした。新たに北前船が停泊する場所として、祇園神社の岬の東側に港がつくられたのです。
祇園神社の岬から東の湾曲した地形を利用したものでした。
さらに下津井沖は、瀬戸内海中央部に近い場所。そのため、東西の潮流の変わり目でした。
下津井港は漁業としてだけでなく、船が潮の流れが変わるのを待つ「潮待ちの港」としても最適な場所だったのです。また風が吹くのを待つ「風待ちの港」でもありました。
こうして北前船が潮待ち・風待ちのために停泊するようになると、下津井には多くの回船問屋が集まり、北前船を相手に活発な取引を始めるようになります。
下津井は漁港や潮待ち・風待ちの港に加え、商港としても栄えるようになったのです。

下津井港で取引された主要なものは、ニシン粕・干鰯(ほしか)と綿・塩などでした。下津井から北前船に綿や塩を売り、北前船からはニシン粕・干鰯を買ったのです。
現在、下津井は児島半島の西南端に位置しています。実は児島半島は、もともと児島という島でした。
安土桃山時代に、岡山城主・宇喜多秀家(うきた ひでいえ)が児島と本土の間の海「吉備穴海(きびのあなうみ)」の一部を干拓します。さらに、江戸時代になると吉備穴海は少しずつ干拓されて、児島は陸続きになりました。
干拓地は塩気を含んでいるため、塩分に強い綿花が多く栽培されるようになります。北前船から買ったニシン粕・干鰯は、綿花栽培の格好の肥料として使用されました。
そして栽培された綿花から取れた綿や、綿を使って製造された製品を北前船へ売るというサイクルが生まれたのです。
また児島周辺では塩田がつくられ、製塩業も盛んであったことから、塩も売られました。
備前と讃岐を渡る連絡港に

下津井は漁港・潮待ち港・風待ち港・商港に加え、新たに旅客港としての役目も生まれます。下津井の場所は、備前と讃岐のあいだで、もっとも陸地間の距離が近いところでした。
このため備前・讃岐を船で渡るのに、もっとも都合が良い場所だったのです。そのため、備前・讃岐間の渡船場所になりました。
江戸時代後半には、児島の由加山の瑜伽大権現と讃岐の金毘羅大権現の「両参り」が盛んになり、下津井には両参りをする旅人が多く集まったといいます。港町には宿も多くありました。
東西南北の海上交通の結節点となった下津井。下津井を治めていた岡山藩は、領地の南の入口となる重要拠点と見なしたのです。
江戸時代初期、岡山藩が下津井城を築いて防衛を固めました。しかし、下津井城は、江戸幕府の「一国一城」の方針により、築城からわずか36年ほどで廃城になっています。
近代では漁港と旅客港としての役目に

明治維新を迎え日本が近代化の道を歩み始めると、明治時代前半には北前船は役目を終えました。その後の下津井は、漁港と本州・四国間を連絡する旅客港として栄えます。
また下津井電鉄によって児島中心部と下津井が連絡され、旅客港としての下津井港の利便性が向上します。
しかし交通の中心が自動車に移るようになり、さらに1988年(昭和63年)に瀬戸大橋が開通。下津井電鉄も廃線となり、旅客港としての役目も終えました。
以降、下津井は漁業の町として存続します。下津井で捕れた海産物は名産として知られるようになり、特にタコは有名になりました。
現在も下津井に残る古い港町の面影

自動車中心の社会が到来したことにより、下津井では大規模な開発がおこなわれませんでした。また児島は繊維業が地場産業であったため、かつての回船問屋の蔵などの建物が、繊維関係の作業場に転用されたのです。
そのため、かつて港町として繁栄した時代を残す古い建造物が多く残ることになりました。
1986年(昭和61年)に、下津井の町並みが岡山県の町並み保存地区に指定されます。
2017年(平成29年)には、日本遺産「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」の構成文化財に。
さらに2018年(平成30年)、日本遺産「荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間~北前船寄港地・船主集落~」の構成文化財になりました。
なお北前船の船頭たちが歌った「下津井節」や、「祇園神社の奉納物・下津井祇園文書」なども日本遺産の構成文化財になっています。