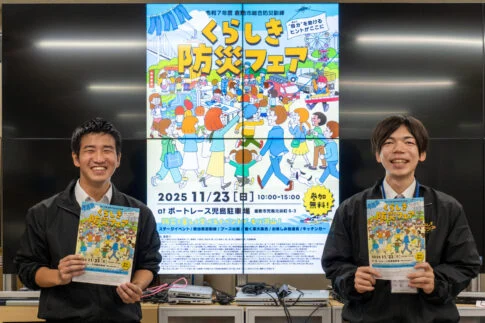外村吉之助の想いが詰まった倉敷民藝館
大原美術館 工芸・東洋館のすぐ近くには、大原孫三郎が建設支援をした日本民藝館についで全国で2番目に開館した民藝館、倉敷民藝館があります。
倉敷民藝館 館長補佐、公益財団法人大原芸術財団シニア・アドバイザーの柳沢秀行(やなぎさわ ひでゆき)さんに館内を案内してもらいつつ、倉敷の民芸品について話を聞きました。

倉敷の民芸について一目でわかる展示室はありますか
柳沢(敬称略)
倉敷民藝館に入って最初の部屋をよく見ていただくと、「民藝とは何か」をつかむヒントがあります。
倉敷は江戸時代、海だった場所です。そこを干拓する過程で、塩に強い綿花の栽培が盛んにおこなわれました。

綿花からできた織物には、真田紐がありますよね。
これを麦稈(ばっかん)で編んで連なったものが、麦わら帽子やバッグになり現在も笠岡市などで作られています。
民芸品というのは、その土地ならではの材料を使ってできているものです。
過去の古いものではなく、現在にもつながる産業のひとつなんですよ。
もちろん、権力者やお金持ちは遠くの土地から良い材料を集め、名のある専門の職人の手による道具を使っていました。
そうしたものを上手物(じょうてもの)とすると、その土地の材料で、おそらくは農民が農閑期などに自ら作って使ったものは下手物(げてもの)です。当然、作り手の名前など伝わらない品々となります。
民藝運動以前は、上手物こそ良いものだとされていましたが、下手物に価値を見出したのが民藝運動です。
つまり、倉敷民藝館には、いわば下手物が多く展示されているわけですね。ただそれは、人々の日々の暮らしを彩り、そして丈夫で長く使えるたくましい道具たちなのです。

特定の作家の作品である「倉敷ガラス」は、なぜ展示されているのですか
柳沢
倉敷ガラスは、小谷眞三(こたに しんぞう)さんが生み出し、今は、その息子の栄次(えいじ)さんへと引き継がれています。
つまり、第二次世界大戦以後は、作者が誰かわかる作品も、丈夫で長く使え 人々の日々の暮らしを彩る品々ならば、民芸の品として扱われるようになりました。
このように、その時代ごとにこの倉敷の地で「良い」とされ生活で使われてきたものが並んでいるのがこの部屋の特徴です。

海外のカゴもたくさんありますよね
柳沢
カゴはまさに実用品です。
役割に応じて形が決まってくるので、作家個人の表現というのはあまり出なくなってしまいます。
それがゆえに、その土地で取れる植物や、その土地の暮らしぶりを反映した作品が見られるのが特徴です。これらは、初代館長の外村吉之助(とのむら きちのすけ)が収集した品々です。
さて、ここまで倉敷民藝館を一緒にまわってみて、ここにある展示作品は現代の暮らしで使っていけそうですか?

家具も一つひとつが大きく、現代のマンションやアパートにはなかなか置けそうにありません。
柳沢
そうですよね。
倉敷民藝館が創設された1948年から外村吉之介が収集に尽力した時期は、われわれのライフスタイルが激変した時期でもあるわけです。今では、畳の部屋がない家も多いし、椅子に座る時間のほうが長い生活です。それに衣類も変われば、産業構造も変わりました。
私たちの暮らしは、時代によって少しずつ変化していますよね。
それとつれて、「民藝とは何か」「民芸品とは何か」の定義も、少しずつ考え直さないといけないかなと思います。ただ根本は、人々の日々の暮らしのなかで普段使いできる品々であることに変わりはないと思います。
倉敷美観地区には、民芸か否かはともかく普段使いできる器や道具を扱っているお店がたくさんあるので、巡ってみてください。お店ごとに印象が異なるので、とてもおもしろいですよ。