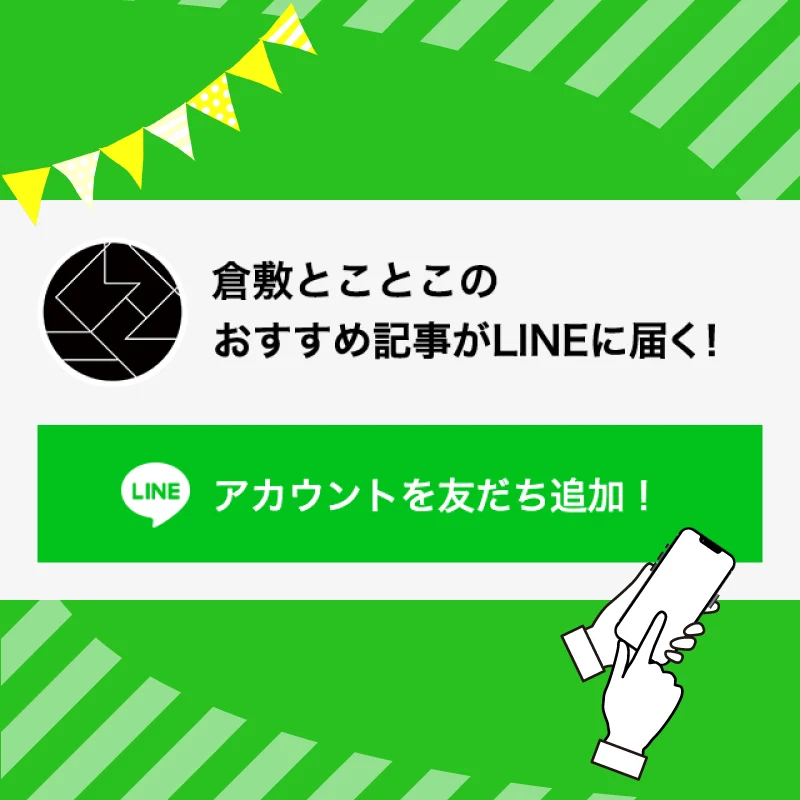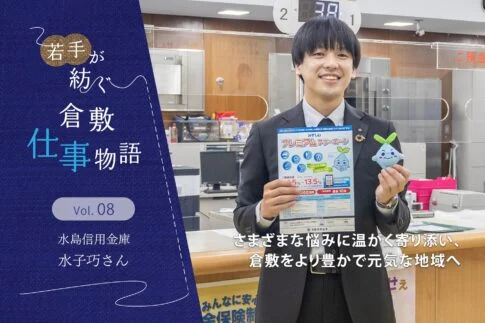2023年12月に関東から倉敷へ移住してきた私にとって、昔からの人々の暮らしが垣間見える邸宅が至るところに残る倉敷の風景は、新鮮です。
町家といえば、白壁の街とも呼ばれる倉敷美観地区が有名ですが、児島にも国指定重要文化財の立派な邸宅「旧野﨑家住宅」があります。
2023年9月には、俳優の菅田将暉(すだ まさき)さん主演の映画『ミステリと言う勿れ』のロケ地ともなった敷地面積約3,000坪の邸宅の歩みと見どころを紹介します。
記載されている内容は、2025年7月記事掲載時の情報です。現在の情報とは異なる場合がございますので、ご了承ください。
目次
旧野﨑家住宅のデータ

| 名前 | 旧野﨑家住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県倉敷市児島味野1丁目11-19 |
| 電話番号 | 086-472-2001 |
| 駐車場 | あり 【 無料 】大型バス 5台 / 乗用車 36台 |
| 開館時間 | 午前9時 ~午後4時30分(午後5時閉門) |
| 休館日 | 月 月曜が祝日であれば、その翌平日 年末年始休館(12/25~1/1) |
| 入館料(税込) | 大人(高校生以上):500円 小中学生:300円 幼 児:無 料 ※30名以上の団体の場合、2割引き ※小中学生・高校生は、土曜日・日曜日・祝日は無料。 ※障害者手帳をお持ちの方は2割引。(本人と付添者1名) ※割引の併用不可 ※小中学生・高校生・引率教員が授業の一環として利用する場合は、無料。 |
| 支払い方法 |
|
| 予約について | |
| タバコ | 完全禁煙(屋外に喫煙スペースあり) |
| トイレ | 洋式トイレ 和式トイレ |
| 子育て | |
| バリアフリー | |
| ホームページ | 旧野﨑家住宅 野﨑家塩業歴史館 |
旧野﨑家住宅について

旧野﨑家住宅は、製塩業と新田開発で財を成した野﨑武左衛門(のざき ぶざえもん)が築き上げた民家です。
敷地面積3,000坪、建物延床面積約1,000坪ある邸宅は、主屋だけでなく日本庭園や蔵なども含めて、当時の面影をそのまま残しています。
1995年に博物館登録され、2006年には国の重要文化財に指定。
2011年には、岡山県の博物館として初めて公益財団法人に認定されるなど、建物の保存だけでなく博物館として当時の文化を継承し続ける施設です。
野﨑家とは
清和源氏(せいわげんじ)を祖として、かつては多田姓・昆陽野姓を名乗っていた野﨑家は、16世紀後半に児島郡味野村に居住するようになったと伝えられています。
旧野﨑家住宅を築いた野﨑武左衛門は、足袋の製造販売をしていましたが、38歳のときに一念発起して味野村・赤﨑村の沖合に塩田を築造。両村の名をとって野﨑姓を名乗るようになりました。
所有する塩田面積は約161ヘクタールにもおよび、大塩田地主に成長。岡山藩の命によって福田新田約700ヘクタールの干拓事業も成功させます。
1890年には、武左衛門の孫にあたる武吉郎(ぶきちろう)が貴族院議員に選出されるなど、倉敷を代表する名家として名を連ねました。
現在も続く、製塩業
「野﨑家の塩」といえば現在も有名で、食塩だけでなく化成品(化学工場で、化学変化を応用してつくられた工業製品)など塩を使った製品が、今もなお作られ続けています。
野﨑家の塩を製造するのは、ナイカイ塩業株式会社。
1829年の創業から一貫して、瀬戸内海に臨む児島半島で製塩業を継続しています。
同じ地で塩業を続けているナイカイ塩業は、最も古い塩会社です。

実はこのナイカイ塩業株式会社の登記上の本社は、現在の旧野﨑家住宅。
旧野﨑家住宅は、入館料のほかナイカイ塩業株式会社のグループ会社の寄付金を活用して運営しています。
専門家が足繁く通う!博物館としての機能も充実

2011年には、岡山県の博物館として初めて公益財団法人に認定された旧野﨑家住宅には博物館としての機能もあります。
児島地区は、第二次世界大戦の際に空襲による被害がなかったこともあり、戦前からの資料が数多く現存。
なかには、鎖国時代に大陸から送られてきた品物もあり、いつ・だれから・どのような目的で届いたものなのか覚え書きも残されています。
美術品が欠けることなくきれいな状態で保管されており、その出自が解るものもあるため、大学や国立博物館の研究者が、旧野﨑家住宅に足繁く通っています。
収蔵品の調査と並行して、博物館としてそれらの展示活動もしています。
展示場所は、当時の蔵。
児島の地に残り続ける建物を生かした展示は、旧野﨑家住宅ならではの景色です。
特別展も開催されています。

「野﨑家のお雛様展」は遡ること明治時代にはすでに始まっており、当時は一日に1,500人もの来館があったと伝えられています。
2025年7月現在決まっている特別展の予定は、以下のとおりです。
- 野﨑武吉郎~塩田王の想いを継いだ男~(2025年7月3日~9月28日)
武吉郎没後100年を記念してゆかりの資料を展示 - こじまブルー Art Festival(2025年10月3日~11月9日)
備前焼作家の木村玉舟(きむら ぎょくしゅう)さんと日本陶彫会瀬戸内支部が、海の生き物を備前焼で表現した作品を展示 - カレンダー企画展「野﨑家の金工展・明治の超絶技巧」(2025年11月13日~2026年1月25日)
岡山の地で細緻な技を極めた正阿弥勝義を中心に展示 - 「野﨑家のお雛様展」(2026年1月28日~4月5日)
- 「おひな同窓会(予定)」(2026年2月21日~3月8日)
展覧会は予告なく変更することがあります
邸内の建築や収蔵品を活用した伝統文化の継承
旧野﨑家住宅は、その名のとおり人が住んでいた家です。
そこには、ここで暮らした人々の暮らしがありました。
1896年に完成した迎賓館、野﨑家別邸迨暇堂(のざきけべっていたいかどう)は、そのような人たちの接待・宿泊・集会の場として使われていました。

現在も、野﨑家に残る能面などを活用して「こじま能」と呼ばれる能の舞台や「こじま落語」など伝統芸能が毎年おこなわれるほか、おひな同窓会の会場としても活用され続けています。
当時から残る収蔵品を、展示するだけでなく文化として残し続ける役割を担っていることが、わかります。
職人の腕が光る!旧野﨑家住宅の見どころを紹介

映画『ミステリと言う勿れ』では、畳張りの部屋が連なる奥行きのある主屋が印象的でしたね。
江戸時代に建てられたこの建物は、畳だけでなく至るところに職人の技が詰まっているとのこと。
学芸員の辻則之(つじ のりゆき)さんに案内してもらいました。
当時から野﨑家を見守り続ける、巨木の数々
国指定重要文化財に指定された建物が立派な旧野﨑家住宅。陰陽石がある日本庭園もまた、圧巻の景色です。

入口に足を踏み入れて最初に目に入る巨木は、モミ。
あまりにも大きくて、つい口をあんぐりと開けて見上げてしまいます。

6月に10日間、薄紫色の花が咲く、ナナミノキも見もの。
花が地面に散った姿は大変美しいです。

また、通りに面して伸びる松の木も立派です。
まっすぐ上に伸びるイメージのある松の木ですが、ここでは通りに伸びていかないように手入れされながら横に伸びる松の木が見られます。
ここまでは、庭に立つ巨木を紹介しました。
巨木は、邸宅内にも存在します。
それは、表書院の屋根を支える17mもの縁桁(えんげた)。

縁桁のアカマツは、現在はもちろん、当時から希少価値の高いもの。
広い邸宅を支えるには、これほど立派な巨木が必要なのかと、まじまじと眺めてしまいます。
どの巨木もしっかりと手入れがされています。
職人のこだわりが詰まった屋根
旧野﨑家住宅では、敷地内にある12の建物が国指定重要文化財です。
その一つ一つが別の作りになっているのもまた見どころで、全国から建築ファンが訪れます。
現在ほど電気が普及していなかった明治時代、広い建物内に明かりを入れる技術が求められました。
邸宅内には、至るところにガラスでできた明かり採りがあります。


「自然光をふんだんに採り入れられるこの設計は、晴れの国岡山ならではでしょう」と辻さんが教えてくれました。
散策時はつい足元ばかり見がちですが、顔をあげて明かり採りにも注目してみてください。
また、日本庭園内にある茶室も見どころです。
五角形の臨池亭(りんちてい)も有名ですが、その手前にある容膝亭(ようしつてい)の屋根に注目しましょう。

手前の薄い板が何層もにも重なってできた屋根は、杮葺き(こけらぶき)という技法で作られています。

日本古来の伝統的手法で、焼失前の金閣寺や銀閣などでも用いられてきましたが、再現できる職人は年々減少。旧野﨑家住宅では、青森県の五所川原(ごしょがわら)から萱材料を仕入れて手作業で修繕をしています。
現在日本で二人しか作れない伝統的な備後の中継ぎ表畳
ところで、畳を踏み比べたことはありますか?
私は、曾祖母の実家が江戸時代から続く民家だったことや茶道をしていることから、和室には慣れ親しんできたつもりでした。しかし、畳の踏み心地を意識したことはなかったように思います。

実は、旧野﨑家住宅に敷かれている畳は「備後の中継ぎ表畳」と呼ばれており、以前は広島県福山市で作られていました。
表皮が厚く、粒揃・光沢があるうえ、青味を帯びた銀白色の美しい藺草(いぐさ)を厳選して使用した使用した高級な畳表です。現在日本で二人しか作れないこの畳は、京都御所の迎賓館にも送られたことがあります。
普段は外から眺めるだけですが、取材時は特別に畳の踏み心地も体験してきました。

藺草(いぐさ)自体に弾力性があり、現代の畳と比べて踏み心地の優しい畳は、一畳約30万円。
旧野﨑家住宅で使用している畳は、約13年に一度張り替えながら大切に守り続けています。
全長42m、9室の座敷を見通す中座敷も、この備後の中継ぎ表畳だからこそ、今もなお圧巻の景色を見せてくれるのでしょう。
使用人思いの野﨑家らしい、ハイカラな水回り
塩田業には、多くの人手が必要です。
野﨑家でも、数多くの使用人が生活していました。
食品でもある塩を扱うからこそ、使用人の過ごす場所が清潔になるような工夫もありました。
その代表が、トイレ。

今でこそトイレがあることは当たり前ですが、当時は使用人のために陶器で作られた便器は少なかったのはないでしょうか。
また、五右衛門風呂もあり、水回りに心配りのされた環境であったことが伺えます。

近くにある台所も、大変広く、開放感があります。
調理器具が説明書きとともに展示してあるので、当時の暮らしに想いを馳せながら見学してはいかがでしょうか。
港と交信した軌跡も、現存
塩田業は、港と邸宅の両輪で進められました。

電話機などが普及する以前に使用されていた掲揚台(けいようだい)が、役目を終えてもなお現存しています。

併設の資料館には、港にある旧野﨑浜灯明台(きゅうのざきはまとうみょうだい)のレプリカもあり、港での塩田業がどのように進められていたのかも、垣間見られます。
2026年度以降は、13~14年間の耐震補強工事がスタート
旧野﨑家住宅はこれからもここにある歴史を後世に伝えていくべく、2026年度から耐震補強工事を予定しています。
広さ約3,000坪(約10,000平方メートル:野球場一面分)もある巨大な敷地のため、段階的に工事がおこなわれるそうです。そのため、長期間にわたって全館休業することはありませんが、今後13~14年間にわたって敷地内のどこかが改修工事している状況が続く見込みです。
紹介したすべてのスポットを見学できるのは、2025年度いっぱい。
数多くの見どころがある旧野﨑家住宅について、学芸員の辻則之さんに話を聞きました。
旧野﨑家住宅のデータ

| 名前 | 旧野﨑家住宅 |
|---|---|
| 所在地 | 岡山県倉敷市児島味野1丁目11-19 |
| 電話番号 | 086-472-2001 |
| 駐車場 | あり 【 無料 】大型バス 5台 / 乗用車 36台 |
| 開館時間 | 午前9時 ~午後4時30分(午後5時閉門) |
| 休館日 | 月 月曜が祝日であれば、その翌平日 年末年始休館(12/25~1/1) |
| 入館料(税込) | 大人(高校生以上):500円 小中学生:300円 幼 児:無 料 ※30名以上の団体の場合、2割引き ※小中学生・高校生は、土曜日・日曜日・祝日は無料。 ※障害者手帳をお持ちの方は2割引。(本人と付添者1名) ※割引の併用不可 ※小中学生・高校生・引率教員が授業の一環として利用する場合は、無料。 |
| 支払い方法 |
|
| 予約について | |
| タバコ | 完全禁煙(屋外に喫煙スペースあり) |
| トイレ | 洋式トイレ 和式トイレ |
| 子育て | |
| バリアフリー | |
| ホームページ | 旧野﨑家住宅 野﨑家塩業歴史館 |